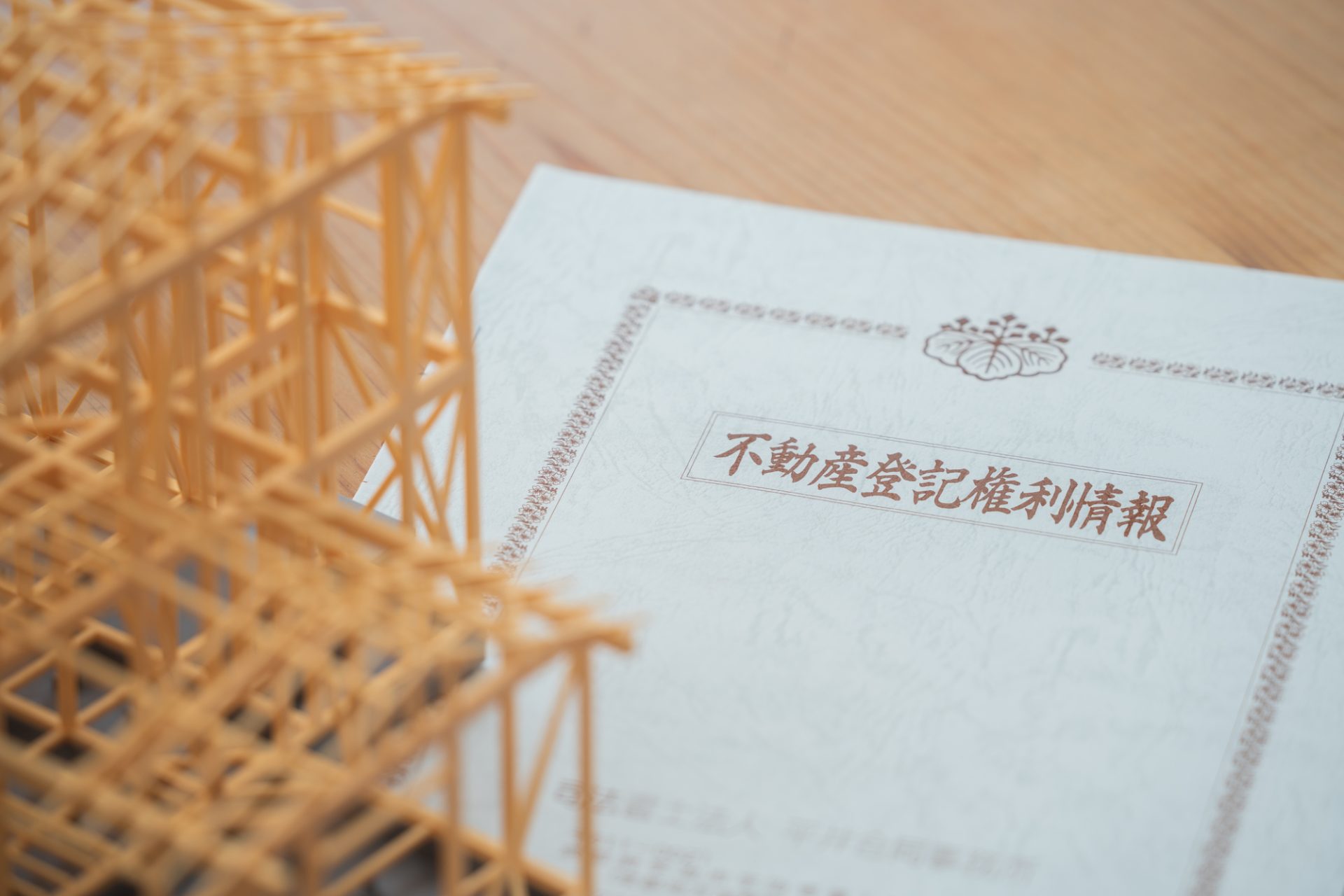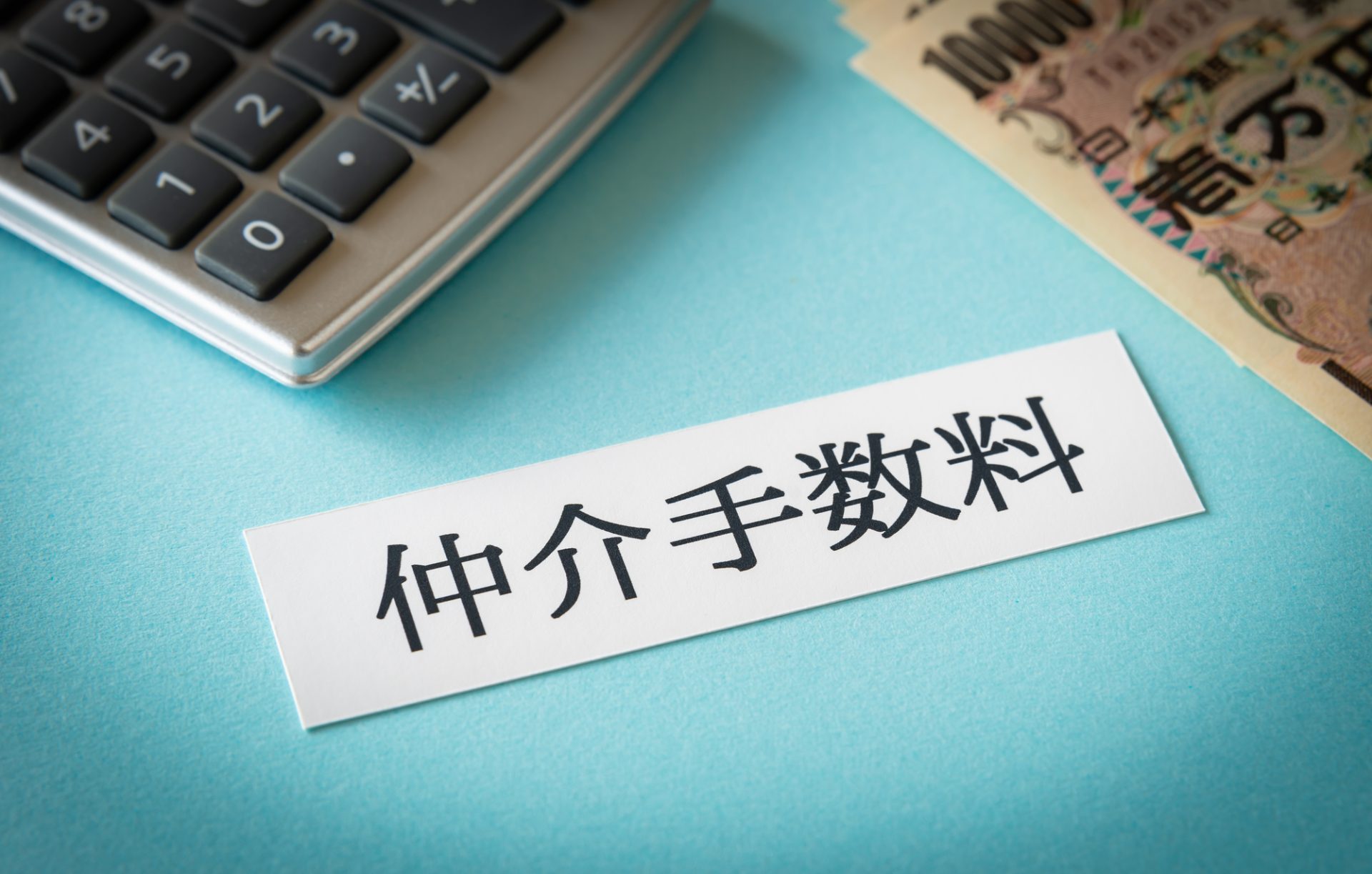土地売却での利益は、確定申告で納税しなければなりません。サラリーマンの給与と異なり天引きなどのシステムがないため、多くの人が頭を悩ませているのではないでしょうか。そこで本記事では、確定申告に必要な書類や手続きの流れについて、詳しく解説します。注意すべきポイントなどについても解説しているため、参考にしてみてください。
目次
土地を手放したら確定申告はするべき?
土地を手放した際に確定申告が必要な場合と不要な場合について、以下の項目から選択してご確認ください。
確定申告が必要なケース
土地を売却する際、確定申告が必要になるケースは4つあります。
- 譲渡所得が発生した場合
- 特別控除の適用を受ける場合
- 先祖代々の土地などで、取得価格が不明の場合
- 損益通算の特例を利用する場合
これらの状況に当てはまる場合は、確定申告を忘れずに行いましょう。
確定申告が不要なケース
不動産を売却しても利益が出ない、または損失が出た場合で、他の所得との損益通算をしないケースについては、確定申告が不要です。ただし、損益通算をすることで節税になる可能性があるので、状況をよくみながら、確定申告をするかどうか検討しましょう。
必要書類一覧【すべてのケース共通】
確定申告に必要な書類を以下から選んでご確認ください。
- 確定申告書第一表・第二表
- 確定申告書第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書
- 不動産の取得にかかった費用の領収書のコピー
- 不動産取得時の売買契約書のコピー
- 不動産売却時の売買契約書のコピー
- 不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー
- 登記事項証明書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票
確定申告書第一表・第二表
譲渡所得や給与所得、事業所得など、所得を申告する際はどのような場合においても、確定申告書第一表・第二表が必須です。これらは税務署や市役所、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
確定申告書第三表(分離課税用)
不動産の譲渡による所得の詳細を記載する書類です。確定申告書と同様に、税務署や市役所、国税庁のWebサイトで入手できます。
譲渡所得の内訳書
不動産売却の詳細を記載するものです。物件の所在地や売却額、購入額、売却にかかった経費、代金受領の状況などを記入します。国税庁から郵送されるので、自分から手に入れる必要はありませんが、必要な場合はWebサイトからもダウンロード可能です。
不動産の取得にかかった費用の領収書のコピー
不動産取得にかかった費用の領収書のコピーは、取得費を証明する上で重要です。取得費には購入金額の他、仲介手数料や取得税、登記費用、測量費用、印紙税などが含まれます。取得費の情報がないと、税額が増える可能性があるため注意しましょう。
不動産取得時の売買契約書のコピー
不動産購入時の売買契約のコピーは、譲渡所得の内訳書で取得費を算出する際に利用されます。この書類がない場合でも確定申告は可能ですが、税額が増える可能性があるため注意しましょう。
不動産売却時の売買契約書のコピー
不動産を購入した際と売却した際の両方の契約書が必要です。これらを紛失した場合は、住宅ローンの借入契約書や登記簿謄本、購入金額が記録された通帳などで、購入を証明できます。
不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー
売却時の費用を確定させるためには、それぞれの費用についての領収証が必要なため、保存を忘れないようにしておきましょう。不動産そのものについての取引にかかる領収書だけでなく、仲介業者への手数料、不動産取得税、登記手数料、契約書の印紙代、アパートなどの取引で住民へ支払う立ち退き料や移転料などが含まれることもあります。
登記事項証明書
登記事項証明書にはいくつかの種類がありますが、確定申告において推奨されるのは「全部事項証明書」です。法務局で発行できるほか、オンラインでの申請も可能です。なお、確定申告において特例を利用する場合は、この証明書が不要なケースもあります。
本人確認書類
確定申告には、マイナンバーと身元を証明する書類が必要です。マイナンバーの確認には、マイナンバーカードや番号付き住民票を利用します。身元確認には、マイナンバーカード、写真付き身分証明書、送付された公的書類、または源泉徴収票と健康保険証などが必要です。
マイナンバーカードがあれば、2つの書類を用意することなく、マイナンバーと身元、両方の確認が可能です。
源泉徴収票
給与所得者が譲渡所得を申告する際は、源泉徴収票が必要です。源泉徴収票自体を提出する必要はありませんが、確定申告書に収入金額や源泉徴収金額を記載することが求められるため、用意をしておきましょう。
必要書類一覧【特例利用時のみ】
特例を利用する際に必要な書類を以下から選んでご確認ください。
- 居住用財産の3,000万円特別控除の特例
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
- 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
- 相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例
- 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除の特例
それぞれの特例と、必要となる書類について、詳しく解説します。
居住用財産の3,000万円特別控除の特例
居住用財産を売却する際、最大3,000万円の特別控除が適用されます。この特例を利用するためには、戸籍の附票や除票、除附票の写し(住所変更がある場合)が必要です。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
10年以上所有した居住用財産を譲渡する際も、軽減税率が適用されます。適用を受けるためには、売却土地の登記事項証明書や戸籍の附票などが必要になります。
特定の居住用財産の買換え特例
居住用財産を買い換える際、特定の条件を満たせば税金の特別控除が適用されます。以下が追加の必要書類です。
- 売却した土地の登記事項証明書
- 戸籍の附票や、附票の除票、除附票の写し(住所変更がある場合)
- 買い換えた家や土地の登記事項証明書、または売買契約書のコピー
また、特に築25年を超える中古住宅に買い換える場合、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が必要です。なお、買い換え先の家が未定の場合は、買換資産の明細書が求められます。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続により居住用財産を譲渡した際、特別控除が適用される場合があります。適用を受けるために必要な書類は以下のとおりです。
- 譲渡所得の内訳書(5面)
- 売却土地の登記事項証明書
- 被相続人居住用等確認書
相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例
相続による財産の譲渡所得に関して、取得費用に相続税額を加算できる特例です。この特例を利用する際に追加で必要となる書類は以下のとおりです。
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成27年1月1日以後相続開始用)
- 相続税申告書のコピー
居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
居住用財産を買い換える際に生じた譲渡損失は、他の所得との損益通算や繰越控除が可能です。この特例を利用するために必要な書類は以下のとおりです。
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の明細書
- 売却した土地の登記事項証明書
- 戸籍の附票や附票の除票、除附票の写し(住所変更がある場合)
- 買い換えた家・土地の登記事項証明書、または売買契約書のコピー
- 買い換えた家・土地の住宅借入金などの残高証明書、または住宅ローンの残高証明書
特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特定の居住用財産の譲渡損失について、特例で損益通算や繰越控除が可能です。この特例を利用するためには、以下の書類が追加で必要です。
- 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
- 売却した土地の登記事項証明書
- 住所変更がある場合は戸籍の附票や附票の除票の写し
- 除附票の写しなど、売却した土地の住宅借入金などの残高証明書
低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除の特例
この特例は、低未利用土地などを譲渡する際、最大100万円までの特別控除が適用されるものです。この特例を利用するためには、低未利用土地等確認書が必要です。
土地を売った後の所得税計算方法
土地を売却した後の所得税計算方法について、以下の項目から確認してください。
特別控除額がある場合は差し引く
適用できる特例がある場合は、必ず特別控除を活用しましょう。
例えば、3,000万円特別控除を適用できる場合、譲渡所得がゼロになることがあり、その結果、所得税や住民税を納める必要がなくなるケースもあります。
ただし、譲渡所得がゼロになった場合でも、確定申告は必須ですので、申告を忘れないようにしましょう。
所得税額を計算する
土地の譲渡所得税は、他の所得と分けて計算されます。計算式は以下の通りです。
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率
税率は、土地の所有期間が5年を超えているかどうかで異なります。
以下は、復興特別所得税を含む税率です。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年以下(短期) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超(長期) | 15.315% | 5% | 20.315% |
注意点: 所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で計算されるため、該当する年の所有期間に注意しましょう。
短期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以内
所得税: 2,800万円 × 30.63% = 857.64万円
住民税: 2,800万円 × 9% = 252万円
長期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える
所得税: 2,800万円 × 15.315% = 428.82万円
住民税: 2,800万円 × 5% = 140万円
さらに、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、「軽減税率の特例」を適用でき、税率がさらに低くなります。
確定申告はいつ実施する?
確定申告の実施時期について、以下の項目から確認してください。
確定申告の期限
不動産売却に伴う譲渡所得の確定申告期限は、売却翌年の2月16日から3月15日です。なお、3月15日が週末に当たる場合は、翌月曜日が期限となります。ただし、所得税の還付申告をする場合は、この期間より前でも申告が可能です。
まとめ
土地売却に伴う確定申告について、以下の項目からまとめを確認してください。
確定申告が必要なケース
土地の売却などで得られる所得は「譲渡所得」と呼ばれます。譲渡所得には、税額が給与所得など、他の所得とは別に計算される「分離課税」の仕組みが採用されています。分離課税の場合、たとえば、土地を売却して大きな利益が出た場合でも、他の所得と合算されずに、所得税を抑えられるなどのメリットがあります。
一方で、確定申告を怠ると、通常の税金に加えて無申告加算税が課されるので、注意が必要といえるでしょう。
確定申告をするべきケース、不要な可能性の高いケースについて解説します。
確定申告が不要なケース
不動産を売却しても利益が出ない、または損失が出た場合で、他の所得との損益通算をしないケースについては、確定申告が不要です。ただし、損益通算をすることで節税になる可能性があるので、状況をよくみながら、確定申告をするかどうか検討しましょう。
土地を売った後の所得税計算方法
土地を売却した後の所得税計算方法について、以下の項目から確認してください。
特別控除額がある場合は差し引く
適用できる特例がある場合は、必ず特別控除を活用しましょう。
例えば、3,000万円特別控除を適用できる場合、譲渡所得がゼロになることがあり、その結果、所得税や住民税を納める必要がなくなるケースもあります。
ただし、譲渡所得がゼロになった場合でも、確定申告は必須ですので、申告を忘れないようにしましょう。
所得税額を計算する
土地の譲渡所得税は、他の所得と分けて計算されます。計算式は以下の通りです。
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率
税率は、土地の所有期間が5年を超えているかどうかで異なります。
以下は、復興特別所得税を含む税率です。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年以下(短期) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超(長期) | 15.315% | 5% | 20.315% |
注意点: 所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で計算されるため、該当する年の所有期間に注意しましょう。
短期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以内
所得税: 2,800万円 × 30.63% = 857.64万円
住民税: 2,800万円 × 9% = 252万円
長期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える
所得税: 2,800万円 × 15.315% = 428.82万円
住民税: 2,800万円 × 5% = 140万円
さらに、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、「軽減税率の特例」を適用でき、税率がさらに低くなります。
確定申告はいつ実施する?
確定申告の実施時期について、以下の項目から確認してください。
確定申告の期限
不動産売却に伴う譲渡所得の確定申告期限は、売却翌年の2月16日から3月15日です。なお、3月15日が週末に当たる場合は、翌月曜日が期限となります。ただし、所得税の還付申告をする場合は、この期間より前でも申告が可能です。
まとめ
土地売却に伴う確定申告について、以下の項目からまとめを確認してください。
確定申告が必要なケース
土地の売却などで得られる所得は「譲渡所得」と呼ばれます。譲渡所得には、税額が給与所得など、他の所得とは別に計算される「分離課税」の仕組みが採用されています。分離課税の場合、たとえば、土地を売却して大きな利益が出た場合でも、他の所得と合算されずに、所得税を抑えられるなどのメリットがあります。
一方で、確定申告を怠ると、通常の税金に加えて無申告加算税が課されるので、注意が必要といえるでしょう。
確定申告をするべきケース、不要な可能性の高いケースについて解説します。
確定申告が不要なケース
不動産を売却しても利益が出ない、または損失が出た場合で、他の所得との損益通算をしないケースについては、確定申告が不要です。ただし、損益通算をすることで節税になる可能性があるので、状況をよくみながら、確定申告をするかどうか検討しましょう。
土地を売った後の所得税計算方法
土地を売却した後の所得税計算方法について、以下の項目から確認してください。
特別控除額がある場合は差し引く
適用できる特例がある場合は、必ず特別控除を活用しましょう。
例えば、3,000万円特別控除を適用できる場合、譲渡所得がゼロになることがあり、その結果、所得税や住民税を納める必要がなくなるケースもあります。
ただし、譲渡所得がゼロになった場合でも、確定申告は必須ですので、申告を忘れないようにしましょう。
所得税額を計算する
土地の譲渡所得税は、他の所得と分けて計算されます。計算式は以下の通りです。
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率
税率は、土地の所有期間が5年を超えているかどうかで異なります。
以下は、復興特別所得税を含む税率です。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年以下(短期) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超(長期) | 15.315% | 5% | 20.315% |
注意点: 所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で計算されるため、該当する年の所有期間に注意しましょう。
短期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以内
所得税: 2,800万円 × 30.63% = 857.64万円
住民税: 2,800万円 × 9% = 252万円
長期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える
所得税: 2,800万円 × 15.315% = 428.82万円
住民税: 2,800万円 × 5% = 140万円
さらに、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、「軽減税率の特例」を適用でき、税率がさらに低くなります。
確定申告はいつ実施する?
確定申告の実施時期について、以下の項目から確認してください。
確定申告の期限
不動産売却に伴う譲渡所得の確定申告期限は、売却翌年の2月16日から3月15日です。なお、3月15日が週末に当たる場合は、翌月曜日が期限となります。ただし、所得税の還付申告をする場合は、この期間より前でも申告が可能です。
まとめ
土地売却に伴う確定申告について、以下の項目からまとめを確認してください。
確定申告が必要なケース
土地の売却などで得られる所得は「譲渡所得」と呼ばれます。譲渡所得には、税額が給与所得など、他の所得とは別に計算される「分離課税」の仕組みが採用されています。分離課税の場合、たとえば、土地を売却して大きな利益が出た場合でも、他の所得と合算されずに、所得税を抑えられるなどのメリットがあります。
一方で、確定申告を怠ると、通常の税金に加えて無申告加算税が課されるので、注意が必要といえるでしょう。
確定申告をするべきケース、不要な可能性の高いケースについて解説します。
確定申告が不要なケース
不動産を売却しても利益が出ない、または損失が出た場合で、他の所得との損益通算をしないケースについては、確定申告が不要です。ただし、損益通算をすることで節税になる可能性があるので、状況をよくみながら、確定申告をするかどうか検討しましょう。
土地を売った後の所得税計算方法
土地を売却した後の所得税計算方法について、以下の項目から確認してください。
特別控除額がある場合は差し引く
適用できる特例がある場合は、必ず特別控除を活用しましょう。
例えば、3,000万円特別控除を適用できる場合、譲渡所得がゼロになることがあり、その結果、所得税や住民税を納める必要がなくなるケースもあります。
ただし、譲渡所得がゼロになった場合でも、確定申告は必須ですので、申告を忘れないようにしましょう。
所得税額を計算する
土地の譲渡所得税は、他の所得と分けて計算されます。計算式は以下の通りです。
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率
税率は、土地の所有期間が5年を超えているかどうかで異なります。
以下は、復興特別所得税を含む税率です。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年以下(短期) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超(長期) | 15.315% | 5% | 20.315% |
注意点: 所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で計算されるため、該当する年の所有期間に注意しましょう。
短期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以内
所得税: 2,800万円 × 30.63% = 857.64万円
住民税: 2,800万円 × 9% = 252万円
長期譲渡所得の場合の計算例
- 譲渡所得が2,800万円
- 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える
所得税: 2,800万円 × 15.315% = 428.82万円
住民税: 2,800万円 × 5% = 140万円
さらに、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、「軽減税率の特例」を適用でき、税率がさらに低くなります。
確定申告はいつ実施する?
確定申告の実施時期について、以下の項目から確認してください。
確定申告の期限
不動産売却に伴う譲渡所得の確定申告期限は、売却翌年の2月16日から3月15日です。なお、3月15日が週末に当たる場合は、翌月曜日が期限となります。ただし、所得税の還付申告をする場合は、この期間より前でも申告が可能です。
まとめ
土地売却に伴う確定申告について、以下の項目からまとめを確認してください。
確定申告が必要なケース
土地の売却などで得られる所得は「譲渡所得」と呼ばれます。譲渡所得には、税額が給与所得など、他の所得とは別に計算される「分離課税」の仕組みが採用されています。分離課税の場合、たとえば、土地を売却して大きな利益が出た場合でも、他の所得と合算されずに、所得税を抑えられるなどのメリットがあります。
一方で、確定申告を怠ると、通常の税金に加えて無申告加算税が課されるので、注意が必要といえるでしょう。
確定申告をするべきケース、不要な可能性の高いケースについて解説します。
確定申告が不要なケース
不動産を売却しても利益が出ない、または損失が出た場合で、他の所得との損益通算をしないケースについては、確定申告が不要です。ただし、損益通算をすることで節税になる可能性があるので、状況をよくみながら、確定申告をするかどうか検討しましょう。
AIで不動産査定!
AIがお持ちの不動産の市場相場を診断